「望まぬ配属だったけれど、いまでは知財が天職」トヨタの知財戦略の礎に貢献した青山高美―「技術者に尊敬される特許」と「誇りの持てる特許業務」を目指して―
INTERVIEWEE
青山 高美
1968年に名古屋大学大学院工学研究科修了。新卒としてトヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車)に入社。以来、知財に関する業務に従事。米国にて海外の特許について学び、帰国後はGM社との訴訟を担当。1990年に特許部(現知的財産部)の部長に昇格。1996年に株式会社トヨタテクノサービス常務取締役に就任し、2000~2006年まで同社の代表取締役社長として会社を牽引。大学での講義も担当したほか、知財コンサルタントとしても幅広く活躍。現役引退後は岡崎市少年少女発明クラブの指導員として活躍中。著書「この人に聞く(社団法人発明協会出版)」のほか、寄稿も多数。
世界にもその名を轟かせ、今や名実ともに日本を代表するトップ企業であるトヨタ自動車。同社で知財戦略の礎を築くことに貢献したのが、青山高美氏だ。
「エンジンの設計に携わりたいと思っていた」と語る同氏が、なぜ知財の仕事をするようになったのか。11年にもわたる米国企業との特許訴訟とは?
今回は、青山氏を招いて、現役時代のエピソードや知財への思いについて話を伺った。

80歳を超えた現在も、知財への情熱は消えない
—【聞き手:松嶋、以下:松嶋】自己紹介をお願いします。
—【話し手:青山 高美氏、以下:青山】青山高美と申します。現役ではありませんが、以前はトヨタ自動車(以下、トヨタ)で知財に関する仕事をしていました。そのあとは、トヨタの子会社であるエンジニアリング会社の社長に就任し、トヨタの知財や研究開発の支援をしていました。また、ロースクールの教授として、11年間ほど学生たちを指導していたこともあります。
—【松嶋】日本を代表する企業の知財戦略の一線で活躍されていたのですね。現在も何かお仕事をされているのですか?
—【青山】80歳を超えたら公式の仕事は辞めようと思っていたのですが、81歳となった現在も知財コンサルタントとして、知財に関する相談にのっています。新規の案件ではなく、昔からの延長線上で継続している案件に絞っているのですけどね。あとは、年に1度ほど大学院で講義をしています。
プライベートでは、ボランティアとして、少年少女発明クラブ(※1)の指導員もしています。
—【松嶋】次世代の発明家の育成に携わられているのですね。
—【青山】ええ。少年少女発明クラブに関連するものとして、発明協会(※2)が主催する全国大会「全国少年少女チャレンジ創造コンテスト」があり、そこに出場することを目標に掲げながら活動しています。
ちなみに、私が関わっているクラブには、2年連続で全国大会に出場している子もいるのですよ。子どもたちが自分で考えて、自分で物を作って、自分の力で夢を叶える。こういったことに関われるのは、とても光栄なことだと思っています。
体験したことは絶対忘れませんし、どこかで必ず役に立つ時がきます。クラブでの活動で、時には失敗することもあるでしょう。しかし、なぜ失敗したかを分析することで、問題解決能力を身につけられます。子どもたちの創造性を育むことに、少しでも貢献できると嬉しいですね。
※1…公益社団法人発明協会が全国211ヶ所に展開している発明クラブ
※2…表彰事業などを通して発明を奨励する事業を行っている公益社団法人

成り行きで入社したトヨタで手に入れた、アメリカ駐在
—【松嶋】トヨタで働かれていた時のこともお聞かせください。入社されたきっかけはなんだったのですか?
—【青山】入社したきっかけでいうと「成り行き」というのが答えですね。
学生の時はパイロットになりたいと思っていたのですが、夢を叶えるためには宮崎県にある航空学校に行くしかありませんでした。私の実家は裕福ではなく、下宿をするような余裕はなかったため、実家から通学できる名古屋大学に進学することになったのです。
その後、卒業後の進路を考えるようになった時に教授からお誘いを受けて大学院に進学することになり、トヨタの民間奨学金制度を活用して大学院に進学しました。
トヨタに就職すると返金を免除される制度だったため、大学院を卒業したあとはトヨタに入社しました。
—【松嶋】当時のトヨタは、会社としてはどれほどの規模だったのですか?
—【青山】私が入社した1968年は、社員数としては4万人ほどで、今の約1/10ほどの規模でした。世界の売上ランキングでいうと、当時はゼネラル・モーターズ(以下、GM)が1位で、トヨタはその1/3ほどの売上でした。日本では日産が1位で「技術の日産、販売のトヨタ」なんて言われていましたね。要は「トヨタは技術力が高いのではなく販売が上手だから売れているのだ」と言われていたわけです。
—【松嶋】今や日本を牽引する存在であるトヨタにもそんな時代があったのですね。
—【青山】そうですね。とはいえ、日本は高度経済成長期でしたし、トヨタ自体も大きく成長している真っ只中でもありました。知財活動にも力を入れ始めている段階で、私が入社した年に知財部が誕生したのです。
—【松嶋】1968年以前のトヨタでは、知財活動をしていなかったということですか?
—【青山】いいえ。それまでは「特許管理課」という形で特許を管理しており、私が入社した年に「特許管理部(後に知的財産部に名称変更)」に昇格しました。
—【松嶋】何かきっかけがあったのでしょうか。
—【青山】当時のトヨタは、いくつかの特許紛争を抱えていたのです。その中の一つには、通常の技術だと思っていたものが別の会社が保有している特許技術だったことで、特許訴訟に発展したものもありました。
発明を起点に誕生した会社であり、誰よりも特許の大切さを理解しているはずのトヨタが、他社の特許があることも知らずに侵害するなんて、こんなに恥ずかしいことはないと。そこで、会社として特許の体制の強化充実を図るために、特許管理部が誕生したのです。
もっと言うと、「特許体制強化充実はトヨタグループ全体の課題である」と、トヨタ自動車トップが率先して、事あるごとにグループ全体に強化充実の号令を発していました。
—【松嶋】会社として注力している課に配属されるとは、当時から期待されていたのですね。
—【青山】どうでしょう。私としては、大学で機械工学を専攻していたこともあり、エンジンの設計に関わる部を希望していたんですよ。特許管理部への配属が決定したと聞かされた時は、少し戸惑いました。
とはいえ、新入社員で反対するわけにもいきませんし、とりあえずは配属された通りに特許管理部で仕事をしていて。半年に1回のペースで上司との面談があり、毎回「エンジン設計に移りたいです」と言っていたら、2年目の時に「そろそろ『特許管理部で頑張る』と言ってくれないか」と言われたこともありました(笑)。
—【松嶋】言ってしまえば、不本意な配属だったのですね。
—【青山】そうですね(笑)。ただ、職場にいる間は、その業務を精一杯やろうという気持ちを持って取り組んでいました。そうして仕事を続けていたら、3年目にアメリカ駐在の話をいただいたのです。経営層からアメリカの特許についても勉強しようという話がでて、英会話を勉強していた私に白羽の矢が立ったそうで。
当時は1ドル360円ほどでアメリカへの直行便もありませんでしたし、海外旅行なんて夢のまた夢の時代です。私は駐在の話を受け入れて、アメリカに行くことにしました。

帰国後に想定外の出来事が!11年かかった特許訴訟とは
—【松嶋】アメリカではどのようなことをされていたのですか?
—【青山】特許法律事務所で実務研修をしていました。あとは、アメリカ特許商標庁の審査官の研修機関であるパテントアカデミーで、アメリカの知財について学びました。また、いくつかの企業を訪問して、現地企業の特許業務の様子を聞くという活動もしていました。
多くの現地弁護士と会う機会も多々あり、個人的にも私的な友人が多くできました。公私に亘る交流を通して多くのことを経験し、アメリカの文化を肌で吸収することで、無意識のうちにアメリカに対する抵抗感を忘れられたのだと思います。当時はインターネットなどもなく、日本にいるだけではアメリカに関する情報に触れる機会がほとんどなかったため、渡米してからは毎日が刺激的でしたね。
—【松嶋】駐在中に、一番印象的だったエピソードがあれば教えてください。
—【青山】「せっかくアメリカに来たのだから、米国特許商標庁のトップである長官にも会ってみたいな」と思い、特許法律事務所のボスに相談したことがあるのです。「長官と会いたいので案内してほしい」と。そうしたら、ボスは「電話したら?」と気楽に言うのです。
友達じゃあるまいし、ましてやアメリカの知財のトップの人に見ず知らずの27歳の若造が電話できるわけがないでしょう。聞き間違えたのかと思って3回ほど聞き直したのですが、回答は全て同じでした。
半信半疑で、自分の秘書をしてくれていた人にも相談してみたら、「電話されては?」とあっさり言われてしまって。これはやるしかないと思い、電話してみたら特別な質問もされることなく面会予約を取り付けることができました。電話してから約束を取り付けるまで、時間にすると2~3分だったと思います。
—【松嶋】実際にお会いしていかがでしたか?
—【青山】とても気さくな方でした。最後には「いつでも会ってあげるから」と言っていただいて、それ以降は月に1度のペースで会っていました。
何者かわからない外国人の若者相手に時間を割いてくれるなんて、アメリカ人は本当にオープンで懐が深いのだなと感じました。ハーバード大学のターナー教授にお会いした時も同様で、何の紹介状もなく会っていただけました。他にもさまざまなエピソードがあり、開かれたアメリカという印象の国で、2年の間、多くのことを経験させていただきましたね。
—【松嶋】帰国されてからも知財の仕事をされていたのですか?
—【青山】ええ。エンジン設計に移動したいという思いはあったものの、アメリカにまで行かせていただいたわけですし、しばらくは恩返しをしなければと、特許管理部で頑張ってから移動願いを出そうと考えていました。
ただ、その思いとは裏腹に、帰国してから2年後の1975年にGMとの裁判が始まってしまったのです。当時の日本では、アメリカの会社と特許訴訟で争うなんてことは前例が無いに等しく、とても衝撃的な出来事でした。その訴訟は11年ほど続き、結局その終結まで、私はずっとその担当をすることになりました。
—【松嶋】訴訟となると、通常は法務部が担当するのでは?
—【青山】そうですね。当時トヨタでは、訴訟の主観部署は法務部で、他の部署、特許管理部も社内体制では合議部署に過ぎませんでした。しかし、これはアメリカでの特許訴訟です。当時のトヨタ法務部は米国特許制度には全く不案内で、ましてや米国での特許訴訟なんて全く経験がありませんでした。米国の一般弁護士との世界は承知しているものの、特許弁護士とは全くチャンネルもない状態だったのです。
したがって、訴訟戦略の検討や訴訟手続きの会議に法務部の担当者が出席はするものの、何の指示も助言もなく。実際の訴訟指揮、進行はすべて特許管理部が担当することになりました。
—【松嶋】具体的にはどのようなことをされていたのですか?
—【青山】訴訟では争う相手と戦わねばなりませんが、その他に社内関係部署の理解と協力を得て、その上で代理弁護士に当方の方針を理解してもらい最善の戦術を展開してもらう必要があります。
また、米国訴訟特有の作業としては、米国訴訟特有の証拠収集手続き(Discovery procedure)があり、膨大な証拠のやり取りがあります。この結果が訴訟の勝敗に大きく影響すること、更にその作業が金銭的にも工数的にも膨大なため、その対応ができずに証拠収集手続きの最中やその初期段階で、不本意ながらも訴訟を和解で終了するケースが少なくないのが現実です。
この事件では、トヨタが相手から入手した資料だけでも13万ページ分ほどあり、相手を攻撃する方法を考えるためにはその資料を翻訳する必要もありました。相手が要求してきた資料を英語に翻訳する必要もあり、それについては13万ページ以上あったと記憶しています。
—【松嶋】膨大な数の資料を翻訳されていたのですね……。
—【青山】ええ。それに加えて、攻撃および防御の戦術を練るために、これらの証拠の内容をすべて分析する必要もありました。この訴訟進行のために、知財部門からは5人が専従で担当し、技術開発部署からも多い時には10数人が専従で応援に来てもらう形で進めていました。膨大な証拠、秘密情報も扱っていたため、訴訟専用の「訴訟室」を特許管理部の横に常設して、作業していたんですよ。ちなみに、この訴訟室は紛争対策用としてごく最近まで利用されていたと聞いています。
—【松嶋】青山さんはどのような立ち位置で訴訟に携わられていたのですか?
—【青山】訴訟の途中で上司が別の部署に移動したため、7年目からは私が特許管理部の課長となり担当していました。
—【松嶋】裁判の結果はどうだったのですか?
—【青山】米国地裁ではトヨタが勝訴したものの高裁で敗訴してしまい、最終的にはトヨタが和解金を支払い、ワールドワイドで双方が主張を取下げるという和解が成立しました。法律論としては、米国特許は有効、トヨタ製品は均等侵害することが確定しました。
なお、参考に述べますと、当時自動車の排気ガス浄化は、米国の他に日本でも法制規制されており、ドイツも大気汚染には非常に高い関心を持っていました。そのため、会社の作戦として、米国、日本、ドイツ3ヶ国の特許の対応を迫られており、トヨタはこの3ヶ国でも争っていました。
結果、ドイツでは連邦高等裁判所で、GM特許は無効が確定。日本ではトヨタが異議申立てをして、GMが補正、分割出願などを繰り返し、最終的に米国での和解を機に、トヨタが異議申し立てを取り下げたため、その時点での補正の請求範囲で特許登録が確定しましたが、トヨタ製品は侵害しない狭い権利範囲で特許登録となりました。国により特許性の判断基準がこのように違うのです。
—【松嶋】GMとの訴訟を終えた時、どのような思いでしたか?
—【青山】結果として米国訴訟では負けてしまったわけですが、GMを恨む気持ちにはなりませんでしたし、最後までフェアに戦ってくれたと思いました。
—【松嶋】フェアに戦ってくれた、というと?
—【青山】当時はジャパン・バッシング(※3)で、アメリカでは反日感情が高まっている時代でした。陪審員裁判をすればGMに有利なことは明らかでしたが、彼らは最後まで陪審員裁判を希望しなかったのです。
GMは特許紛争では話し合いでの解決を基本としており、原則訴訟はしないという方針でした。それは今も変わりありませんし、訴訟データを見てもその通りです。さらに加えると、米国での特許訴訟件数は日本よりはるかに多いですが、判決数を人口比、GDP比でみるとむしろ日本の方が多いです。「アメリカは訴訟社会」という言葉もありますが、誤解がないようにしたいものです。
—【松嶋】先ほど「アメリカ人はオープンで懐が深い」とおっしゃられていましたが、ここでも同じように感じられたと。
—【青山】ええ。それに、11年も訴訟をしていると、相手の担当者とも絆が生まれると言いますか。信頼関係を築くことができました。和解が成立した後のトヨタとGMは、とても良好な関係だったのですよ。別件の特許で悩ましい状況の際に、その解決方法について国際電話で相談したりされたりすることが数回ありましたが、全て円満な解決ができて、互いにハッピーでした。
さらに、そうした電話相談をきっかけにドイツの自動車企業とも連絡をとれるようになり、日米独の自動車会社との信頼関係が太くなりました。 どんな仕事であっても、最後の接点は人と人なのだなと。人と人の心が通じ合っているか、お互いに信頼しているか、それがとても重要なのだと実感しました。
GM訴訟を遂行したことで特許管理部の能力が評価され、社内での存在感が非常に高まりましたし、部の地位向上につながる良いきっかけとなりました。
※3…欧米の政府・企業が日本を非難すること。1980年代は日本の自動車の輸出が増加したことで米国の自動車産業の業績が悪化し、失業者が増加したため、米国内では日本を非難する声が多くあがっていた。
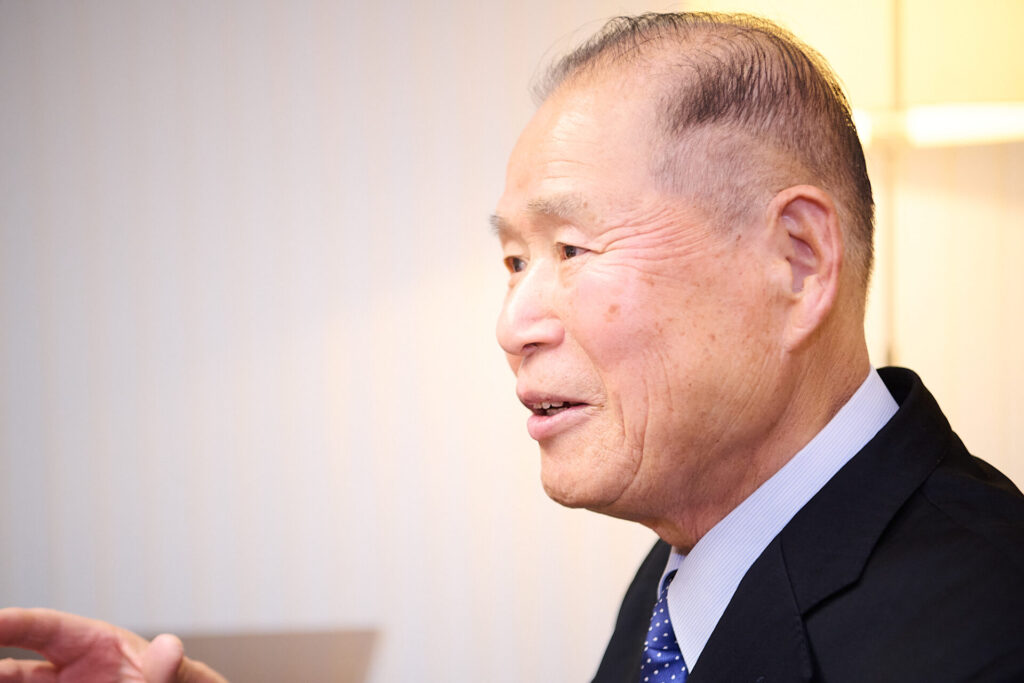
望まぬ配属をきっかけに、気づけば知財が天職となった
—【松嶋】GMとの訴訟が終了したあとは、どのようなことをされていたのですか?
—【青山】特許に対する対応を強化する施策を進めていました。というのも、GM訴訟を進めるなかで、GMの特許出願公開公報を見落としていたことが判明したのです。そこで、他社特許対応のプロジェクトを立ち上げ、他社の特許の監視体制の強化を、トヨタ自身、そしてトヨタの取引先にも徹底するシステムを構築しました。
また特許の出願数を増やす、要は発明を活性化しようという活動も1972年から実施していました。GMとの訴訟では攻撃されっぱなし(こちらから撃ち返す弾がない)だったことを反省し、他社にも攻撃できる、実用的な弾(特許)を取得しようという意識づけもしながら、発明の活性化の活動を一層推進してきました。
—【松嶋】知財を推進するべく積極的に活動されていたのですね。
—【青山】ただ、ある程度すると、無駄な特許も出てくるようになってしまって……。些細な技術であっても特許を出願するようになってしまいました。ある時、トヨタの特許を侵害していると思われる他社へ侵害警告状を発信しようと担当役員に決裁を上げたところ「こんな発明で侵害警告をするのは、恥ずかしいからやめとけ!」と一喝されたこともありましたね。
トヨタ特許管理部内でも、特許出願の質を問題視する事例が度々見られるようになったこともあり、1984年に業務改善の一環で、特許出願の在り方が取り上げられ、特許出願の成果と目的がテーマになりました。それにより、明らかに実施する見込みもない、保護する価値もないものが散見されたため、出願基準の見直しをすることになりました。
結果、明らかに特権権利化の意義のないもの、発明としてはレベルが低く、わざわざ独占権で保護するには相応しくない発明は特許出願しない、ただし、第三者に権利化されることを回避するために発明を公開することにしました。こうして、トヨタでは、量から質への方針変換がなされ、これが定着していきました。
そうこうしていたら、別の会社から、レベルの低い技術の特許でトヨタへ侵害警告状が来たこともありました。侵害の可能性が高い事例があったため、当該技術を利用している設計部署に侵害回避策を検討するように指示をしたところ「こんなつまらない技術の特許にも実施料を払わなくてはならないのか。特許はつまらないな!」、更に「うちは社内には厳しいけど、社外に甘いのか!?」とまで言われてしまい……。
—松嶋】それは心に刺さる言葉ですね。
—【青山】自分の仕事を否定されたような、非常に悲しい気持ちになったのを覚えています。しかし技術者からすると、些細な技術のためにお金を払ったり、設計を変更したりするなんて、骨が折れるだけの無駄な作業であるのも事実で。つまらない特許をとるために、つまらない技術開発に金と時間を投入することは、真に高度革新的な技術開発に投入すべき貴重なエネルギーを浪費していることと同じです。一企業のみならず、産業界全体にとっても、その製品の消費者、社会全体にとっても、損失と言わねばならないと思いました。こんなことをしていたら技術の進歩も遅れてしまうと。
「この種の発明で特許侵害を主張して紛争をしていては、お互いに自社の技術者から非難され、特許部門はそのために貴重な資金と労力を浪費することになり、互いに不幸としかなり得ない。この種の発明は権利化することを自粛し、ただし、第三者に権利化されることを防止するために、日本自動車工業会知的財産部会として当該技術を公開しようではありませんか?」と1989年に提案した所、全会一致で大賛成を得ました。こうして、1989年12月から「自動車技術事例集」を出版することになったのです。
また、量から質への変換が定着しつつあるとき、特許庁での面接審査の折に、園田審査官からトヨタの特許出願の発明について聞かれた質問で印象的だったものがあります。
—【松嶋】詳しく教えてください。
—【青山】「この発明の原理はなんですか?」と問われたのです。これは、発明の本質を追及する問でした。これに大いに刺激を受け、その追及方法をトヨタ流に深めて、トヨタでは発明の「解決原理」を追及することを始めました。
技術および発明の本質を追及することにより、真の発明、基本発明を追及することができます。これにより、いわゆる基本発明の解決手段を把握できることになり、広く、強い特許権を取得することができるようになりました。こうして、強く広い特許を育てながら、パテントポートフォリオの形成を構築へと展開されていきました。
この分析は、技術者にとっても技術の本質追及は有用でしたが、通常技術者の仕事の進め方は、技術問題の解決ができる(発明する)と、できるだけ早く商品化をしたいという欲求が強く、その解決した技術の本質を追及するニーズを考えないか、その余裕がない宿命にあります。そのため、本質の追求は知財部門の人に任されることが多い。
しかし、この手法を技術者にも習得してもらうと、発明の都度に自然に技術者自身が発明の本質を追及するようになり、技術に精通した技術者による高度な分析がスピーデイに行われ、優れた発明、強く広い特許の誕生を達成することができると考えます。
—【松嶋】お話をお伺いしていると、青山さんはトヨタの知財戦略の礎を築かれたのだなと思いました。そのあと、子会社の社長就任に至るまでの経緯もお聞かせください。
—【青山】特許管理部から原価企画の部署に異動して、3年ほど経った頃に、経営層から「トヨタテクノサービスの前社長が定年退職することになったから、この会社へ出向してほしい」とお声がけいただいたのです。
結果として、トヨタには50歳まで在籍し、2000年にトヨタテクノサービスの社長に就任しました。トヨタテクノサービス(その後合併もあり、トヨタテクニカルデイベロップメント株式会社に名称変更)では10年ほど働いていましたね。
また2004年からは、名城大学のロースクールで知財に関する講義もしていました。
—【松嶋】社長業の傍らで、さまざまなお仕事をされていたのですね。
—【青山】ええ。2006年から2016年までは名古屋市立大学の理事して、その後同大学で講師もしていましたそのほかにも、株式会社メルコホールデイングスなど、いくつかの会社で監査役をしていました。
そうやって活動をしている内に知財に関する相談も受けるようになって、知財コンサルタントの仕事も増えていったという流れですね。
—【松嶋】当初は自分の希望ではなかった知財のお仕事が、続けていくことで天職になったのですね。
—【青山】そうですね。結局のところ、仕事をする上で大切なのは、この仕事の目的は何か、会社の使命は何かを常に考え、自分の仕事にプライドを持って社会の役に立てるように努力をし続けることなのだと思います。私の場合は一時的な利害に惑わされることなく、後々になっても誇りを持てる仕事のやり方を考えていました。
また特許によって技術者が技術革新をし、尊敬される特許の発明を促進するとともに、知財に関わる人が自分の仕事に誇りを持つためにはどうすれば良いのか?」を常に考えながら仕事をしてきました。現役は引退しましたが、これからもその熱意を持ち続けたいですね。

KEYPERSONの素顔に迫る20問
Q1. 出身地は?
愛知県一宮市です。
Q2. 趣味は?
ゴルフと油絵です。
Q3. 特技は?
特技と言えるのかわかりませんが、強いて言うなら人と楽しく過ごすこと。
Q4. カラオケの十八番は?
最近はカラオケにあまり行かなくなりましたが、以前は西田敏行さんの「もしもピアノが弾けたなら」をよく歌っていました。
Q5. よく見るYouTubeは?
Youtubeは見ていません。
Q6. 座右の銘は?
「感謝」です。私がここまでやってこれたのは、家族や周囲の人たちのおかげですから。
Q7. 幸せを感じる瞬間は?
今はずっと幸せです。
Q8. 今の仕事以外を選ぶとしたら?
パイロットを目指していた時期もありましたが、小学生のときは小説家に憧れていました。私は文章力や表現力が豊かな方ではありませんから、小説家になるのは到底無理だったと思うのですけどね(笑)。
Q9. 好きな漫画は?
昔読んでいたもので好きな作品は『サザエさん』と『ドラえもん』です。
Q10. 好きなミュージシャンは?
特定の人は思い浮かびませんが、音楽のジャンルでいうとクラシックが好きで、コンサートにもよく行っています。
Q11. 今、一番会いたい人は?
トヨタの5代目社長を務めていた豊田英二さんです。私だけでなく、トヨタ社員の多くは英二社長の人柄に惚れ込んでいたと思います。懐が深く、社員一人ひとりを大切にする方でした。
Q12. どんな人と一緒に仕事したい?
自分でやり切る人。失敗しても良いから、自分で考えて判断して最後までやり切る人が良いですね。言い換えると、自立心のある人とも言えるかもしれません。
Q13. 社会人になって一番心に残っている言葉は?
GM社との訴訟が終わったあとに、英二社長から言われた「いい勉強になったね」という言葉です。これは、私への言葉でしたが、会社全体として勉強になったという意味だったと思っています。
英二社長は、そういう思いやりと謙虚さを忘れない人でした。あえて、もう一言追加しますと、GM訴訟を受けて戦うことが議題になった取締役会の席で営業担当の専務が「GMと訴訟をして、トヨタをつぶす気か!」と、特許担当役員を叱責したときに、英二社長は「これからはトヨタも海外でビジネスをする時代だ。海外では主張すべきことがあれば、しっかりと主張することが重要である」と言われたのです。それにより、取締役会は静まり、訴訟決行が無事決定されました。英二社長の優れた大局観と人の心理を巧みに読んだ発言は名文句と、今でも忘れられません。
Q14. 休日の過ごし方は?
少年少女発明クラブに参加する以外には、その準備に時間を費やしていることが多いですね。あとは趣味の油絵を描いたり、老人会に参加したりしています。
Q15. 日本以外で好きな国は?
アメリカです。
Q16. 仕事で一番燃える瞬間は?
大きな仕事を任された時。
Q17. 息抜き方法は?
趣味に打ち込みます。
Q18. よく使うアプリやサービスは?
スマホの使い方もよくわかっていませんので……。その中でも使うとしたら、電話とLINEぐらいでしょうか。
Q19. 学んでいることや学んでみたいことは?
AIについて少し勉強してみたいなと思っています。つい先日、ChatGPTを使用した際に、1秒も経たないうちに回答があって驚きました。
Q20. 最後に一言
感謝の気持ちを忘れず、謙虚に生きましょう。
次世代の知財パーソンに伝えたい想い
—【松嶋】日本が成長していくためには、特許、ひいては知財をもっと有効活用していく必要があるのではないかと思います。
—【青山】そうですね。日本の国際競争力は年々落ち続けています。特許に関しても、1990年代ごろはドイツに次いで特許審査が厳しい国だったため、日本で特許を取得すると、それだけで箔がつくと言われていました。しかし現在では、外国企業から「これは日本ではなく、アメリカで特許されているのだ!」と言われるほどになってしまいました。日本の特許価値が、世界ではこのように見られていることを忘れてはいけません。
現役世代で頑張っている方々には、特許情報を活用して研究指針に役立ち、社会をリードする知的財産の本質を見極めて、強く尊敬される知的財産権として保護・活用し、技術者からも社会からも尊敬さる知的財産制度の運用、構築にご尽力をしていただきたいと思います。
そして、知財業務を担当される人も、知財戦略を駆使して、誇りに思える知財の世界を構築していただきたいと思っています。今や、国際的に広く社会に利便性を供与する標準技術が利用されており、標準必須特許の活用が注目を浴びつつあります。と同時に、課題も話題になっています。残念ながら、標準必須特許と宣言されているものの中に有効性が危ぶまれる特許が多く含まれているというレポートもあります。尊敬される知財制度の発展がみられることを願っています。
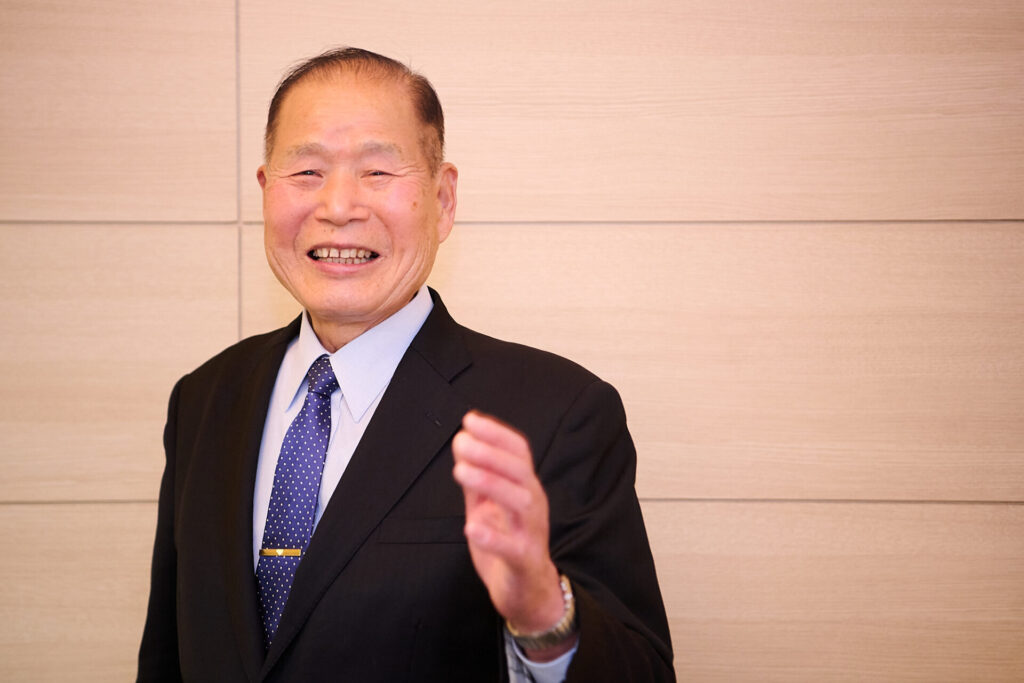
—【松嶋】最後に、読者へのメッセージをいただけますか。
—【青山】ほとんどがデジタルを経由する時代になっていますが、最終的な人と人とのコミュニケーションがなくなることはないでしょう。人は1人では生きていけません。周囲に支えられて生きているのです。
私は、50年以上の知財に関わることができて、そのおかげで国内外の多くの出会いを頂き、本当に充実した素晴らしい人生を送ることができています。私がこのような人生と巡り会えたのは、今までかかわってきた企業やその関係者、更に、周囲の人のおかげです。人を信頼し、感謝の気持ちを忘れずに、ある時には他人の協力を仰ぎながら、自らを励ますことで、人生を切り拓いていけるのではないでしょうか。
また、私がアメリカ駐在で学んだことは、踏み出すことの大切さです。
「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つかる。門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。」
これは聖書に書かれている有名な一節です。目指すものがあるのであれば、ぜひ門を叩いてみてください。まずは踏み出すことで、さまざまなことができるようになると思います。
【クレジット】
取材・構成/松嶋活智 撮影/原哲也 企画/大芝義信
