「知財は国際競争力を高めるカギ」NECの吉村俊秀を魅了した知財の世界
INTERVIEWEE
NEC 弁理士・特定侵害訴訟代理人・MBL(Master of Business Law)
吉村俊秀
一橋大学大学院(知財専攻)修了。NECの法務部門、中央研究所・知的財産部門、エアロスペース・ナショナルセキュリティ(以下:ANS)事業領域にて、30年に渡って知財・技術法務の業務に従事。スマホ等で広く利用されている、国際的な音声符号化規格であるMPEG-4 Audio特許プール立ち上げなど様々な重要プロジェクトに参画し、9,000件超の案件経験に基づく様々な知財/技術取引への対応力、事業に密着した「現場」での知財マネジメントの実行力などを磨いてきた。
弁理士とは:弁護士や税理士、行政書士と同じく、八士業に分類される職業の一つ。知的財産(知財)のスペシャリストとして「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」を取得したいクライアントのために、特許庁への手続きを代理で行うことを主な仕事とする。知財の取得だけでなく、模倣品などのトラブルに関する相談も受け付けている。
特許権:程度の高い発明、技術的アイデア(例:歌唱音声の合成技術など)
実用新案権:発明ほど高度ではない小発明(例:鉛筆を握りやすい六角形にするなど)
意匠権:物や建築物、画像のデザイン(例:立体的なマスクなど)
商標権:商品またはサービスを表す文字やマークなど(例:会社のロゴなど)
1899年、日本初の外資系合弁企業として設立された日本電気株式会社(以下:NEC)。日本を代表するITサービス・社会インフラ事業者である同社は知財戦略にも力を入れており、令和6年度の知財功労賞「特許庁長官表彰デザイン経営企業」を受賞している。(※)
吉村俊秀氏は、そんなNEC ANS領域のCIPO(Chief Intellectual Property Officer:知的財産最高責任者)として第一線で活躍し続けている知財パーソンだ。 同氏が、なぜ知財の道を進むことになったのか?これまでの道のりと、未来への展望を伺った。
※…知的財産権制度の発展・普及・啓発に貢献した個人及び知的財産権制度を活用した企業を表彰するもの

事業・技術・知財が連動した三位一体の知財戦略を推進する司令塔として活躍
—【聞き手:松嶋、以下:松嶋】自己紹介をお願いします。
—【話し手:吉村 俊秀氏、以下:吉村】NEC ANS領域のCIPOとして、知財戦略を立案・推進している吉村俊秀と申します。
—【松嶋】具体的にはどのような業務を担っているのですか?
—【吉村】一言でいうと、事業戦略や技術戦略と連動した知財戦略推進の司令塔です。
具体的には、多数の部門・関係会社からなるANS領域の知財司令塔として、CIPO推進会議メンバーを牽引し、知財戦略の立案と推進を担っています。また、私の配下では、次の4つのチームの皆さんに活躍いただいています。
①各組織の知財責任者と一体となった知財推進の実現を目指す「知財管理チーム」
②経営層への知財インテリジェンス提供を目指す「知財調査チーム」
③知財戦略に沿ったターゲット知財発掘を目指す「知財発掘チーム」
④それら①~③の活動を支える「管理支援チーム」
—【松嶋】ANS領域では、主にどのようなビジネスを行っているのですか?
—【吉村】海中から地上、空、宇宙まで、高い技術力を強みに、国の安全・安心を守るための仕事を行っています。
例えば、「空」の安全のために、GPSを利用した航空機の進入着陸を支援する着陸誘導システムを日本で初めて実運用システムとして開発し、東京国際空港向けに納入するなど、最適な運航を支える航空管制システムの高度化を支えています。
また、「宇宙」へ目を向けると、小惑星探査機「はやぶさ」と「はやぶさ2」の開発にも大きく貢献しています。システムインテグレータとして、システムの設計、製作、試験、運用を担当し、バス機器やイオンエンジンなど多くの搭載機器も担当しました。
最近では、21世紀の社会課題の解決、進化する多種多様な通信デバイスの高品質・効率運用のため、衛星コンステレーションの利用を通じた社会価値創造にも力を入れています。
—【松嶋】組織としてはどれくらいの規模なのでしょうか?
—【吉村】私の所属するANS領域は、関係部門・関係会社あわせて数千人規模の組織となります。同組織の知財活動を、私とCIPO推進会議メンバー約60名の「知財Oneチーム」として推進しています。

熾烈なグローバル知財ライセンス交渉をきっかけに、知財の面白さに魅了された
—【松嶋】NECに入社されたきっかけは何だったのですか?
—【吉村】学生時代にインドネシアに留学したことがきっかけです。
そこでNECがインドネシアを含めた東南アジアの国々に通信インフラを提供していると知り、自分が勉強したことを生かして社会課題の解決に貢献したいと思ったため、1993年にNECに入社しました。
—【松嶋】入社してしばらくは法務部に所属されていたそうですね。そこではどんなことをされていたのですか?
—【吉村】法務部では、ライセンシングやアライアンス、技術移転など、さまざまなことを担当していました。
—【松嶋】そこからどのようにして、現在のような仕事や弁理士を目指すことになったのですか?
—【吉村】一番大きな転機となったのは、2001年の中央研究所への異動です。そこで知財の本当の面白さに気がつきました。
特に、その時に経験したMPEG-4 Audio特許プール立ち上げ活動において、欧米亜企業との熾烈なライセンス交渉等を通じて、もっと高いナレッジや知見が必要と痛感し、そのプロフェッショナル性の担保の一環として知財のプロ「弁理士」「特定侵害訴訟代理人」を目指すことを誓いました。
ただ、そのころは業務が最も忙しかった時代で、さらに家庭では子供が産まれたばかりの頃でした。そのようななかでしたが、なんとか毎日朝4時に起きて勉学に打ち込みました。勉学に打ち込める環境を作り、かつ弁理士試験のための決して安くない予備校費用を自身の貯金から援助してくれた「妻」には本当に感謝しかありません。
また、小泉内閣で打ち出された「知的財産立国」にも大きな刺激を受けました。当時の私は日本の国際的な競争力が落ちていることに危機感を持っていました。そんな時に知的財産立国に関するニュースを見て「知財は日本の国際競争力を高めるためのカギなのだ」と改めて思ったのを覚えています。
—【松嶋】それらが重なって、知財を追求しようと思われたのですね。
—【吉村】ええ。中央研究所での知財業務を通して、世界への貢献と会社利益への貢献とを両立することができる知財の素晴らしさを実感しました。
そして、重要プロジェクトへの参画等のためのANS領域への期限付き異動(2008年)についても、事業開発の「現場」をより深く知るうえで、大きな転機となりました。
その際に、実は2年で元の部署へ戻ることとなっていたのですが、当時の上司に「現場と密着した知財の仕事を極めたいです」と伝えて、ANS領域に残ることにしたのです。
そこからさらに知財を追求し続け、CIPO補佐を経て、2023年にANSビジネスユニットが設立された際に、CIPOを拝命いたしました。

日本を元気にするためにも、知財を追求し続ける
—【松嶋】ライセンスビジネスの成功のポイントはどこにあると思われますか?
—【吉村】仲間作り、企業連携ですね。MPEG-4Audio特許プールがNECのライセンスビジネスとして成功したのは、技術づくりに加えて「仲間づくり」がうまくいったからです。
フランステレコム、サムソン、ドルビー等の様々なバックグランドをもつ各国の有力企業が、それぞれ自己の利益を最大化しようとしている中で、泥臭くコミュニケーションを続けてWin-Winの関係を作り上げていくことがポイントだったのではないでしょうか。
—【松嶋】技術力が高いだけではダメだと。
—【吉村】おっしゃる通りです。開発した側と利用する側の両方が得をする仕組みができてこそ、ライセンスビジネスは成り立ちます。どれだけ画期的な技術であっても、利用する側のメリットが少なければ、使われなくなってしまいますから。
また、ライセンスに限らず知財を適切にビジネス活用するためには、世界的なビジネスの変化を常にキャッチアップすることも重要です。
—【松嶋】具体的に教えてください。
—【吉村】例えば、日本はかつて「モノづくりの国」「特許大国」と呼ばれていましたよね。良いものをリーズナブルな値段で大量に製造し、市場に提供して世界を席巻していく。そういったビジネスモデルにおいては、製品、製造に関する技術の特許を取得するだけで、ビジネスにも大きく効いていたと思います。
ところが、社会はモノ消費からコト消費へ変化し、グローバルで主流のビジネスモデルも大きく変化していきました。それに伴い、知財についても、モノの技術だけではなくエコシステム等のコトの部分での特許を取得することが極めて重要になっていったのです。
日本の少なくない企業は、そういったグローバルの変化にまだ十分に対応しきれず、従来スタイルの延長を続けてしまったため、国際競争力が落ちてしまったのではないかと。
—【松嶋】先ほどお話されていた通り、日本経済が低迷し続けているのには、知財を適切に活用できていなかったことも関係しているのですね。
—【吉村】逆に言えば、知財を適切に活用できれば、日本経済を盛り上げることができるはずなのです。私としては「知財で日本をもっと元気に」をビジョンとしながら、これからも知財の創出・保護・活用を通じた事業利益の最大化について追求していきたいと考えています。

KEYPERSONの素顔に迫る19問
Q1. 出身地は?
兵庫県神戸市です。
Q2. 趣味は?
ランニングです。また、最近では学生時代にやっていた短距離走にもチャレンジしています。
Q3. 特技は?
より良いものを創出するため「人と人とをつなぐ」こと。
Q4. カラオケの十八番は?
Mr.Childrenの「Tomorrow never knows」です。
Q5. よく見るYouTubeは?
これから観たいという意味で良ければ、『佐久間宣行のNOBROCK TV』です。 素晴らしいコンテンツを世に創出し続ける佐久間信行さんを、ビジネスパーソンとしてもとても尊敬していて、彼のラジオ番組もよく聴いているんです。これまであまり時間がとれずYouTubeは未視聴ですので、近々ゆっくり観たいですね。
Q6. 座右の銘は?
人生・仕事、楽しく。
Q7. 幸せを感じる瞬間は?
大きな成果を出すことができて、仲間と「ありがとう」と言い合える瞬間ですね。
Q8. 今の仕事以外を選ぶとしたら?
やっぱり、今の仕事が良いですね。
Q9. 好きな漫画は?
『チ。 ―地球の運動について―』です。 15世紀のヨーロッパを舞台に、禁じられた地動説を命がけで研究する人間たちの生き様と信念を描いた作品で、漫画としてももちろんとても面白いし、また、自身の業務への向き合い方について深く考えさせられる作品でした。 NHK総合テレビでアニメ化されましたので、ご興味のある方はぜひ観てみてください。
Q10. 好きなミュージシャンは?
玉置浩二さん、幾田りらさんなど、素晴らしい癒しの声を持った方々。 最近では、サブリナ・カーペンターの「Please Please Please」という曲をよく聴いています。
Q11. 今、一番会いたい人は?
サブリナ・カーペンターのコンサートへ行ってみたいです。会いたいというよりは、生歌を聴きたいですね。
Q12. どんな人と一緒に仕事したい?
評論するのではなく、どうすれば前に進んでいけるかを一緒に考えられる人。
Q13. 社会人になって一番心に残っている言葉は?
質問の意図とはズレるかもしれませんが、社内貢献の表彰式で表彰された時に、一緒に苦労してきた先輩から思いがけずいただいた「ありがとう」の言葉が今も心に残っています。
Q14. 休日の過ごし方は?
知財の力をつけるための自己研鑽をしたり、スポーツをしたり、音楽を聴いたりして過ごすことが多いです。
Q15. 日本以外で好きな国は?
ダイナミズムという意味では、アメリカです。
Q16. 仕事で一番燃える瞬間は?
目標を立てて、それが達成された瞬間ですね。
Q17. 息抜き方法は?
ストレッチ、インターネットラジオで音楽ヒットチャートを聴くこと。
Q18. 好きなサービスやアプリは?
インターネットラジオ「TuneIn Radio」です。
Q19. 学んでいることや学んでみたいことは?
知財アナリティクスについて学んでいます。そして、ANS事業・技術戦略の検討などにおいて、さらに役立つ情報を提供できる「知財アナリティクスのプロ集団」を育成・強化していきたいです。
Q20. 最後に一言
「意思」があれば想いは必ず叶う、と信じています。

社内外と連携して日本をエンパワーメント
—【松嶋】今後の展望についてもお話いただけますか。
—【吉村】事業戦略や技術戦略の立案を担うキーパーソンとの連携をさらに深め、知財戦略の強化・アップデートを継続し、新事業の創出や既存領域の強化へさらに力を入れていきたいです。加えて、経営層への経営判断材料となれるよう、外部動向も踏まえた知財インテリジェンスの分析・発信も強化していきたいです。
しっかりとした知財戦略があれば、ビジネスの確実性を高めることができますし、リスクを最小限に抑えられるでしょう。緻密な知財戦略を立てられる知財パーソンになるためにも、研鑽を積んでいくとともに、社内外の方々との連携も強めていきたいですね。
—【松嶋】外部の弁理士等と協力すれば、より大きなことができそうですね。
—【吉村】そうですね。まずは社内の弁理士が第一線として知財戦略を推進し、適宜適切に外部の尖った専門領域を持つ弁理士や、産・官・学のキーパーソンとも協力しながら進んでいくことで、より大きなことに挑戦できるようになるはずです。それが積み重なれば、日本をエンパワーメントすることにもつながると思います。
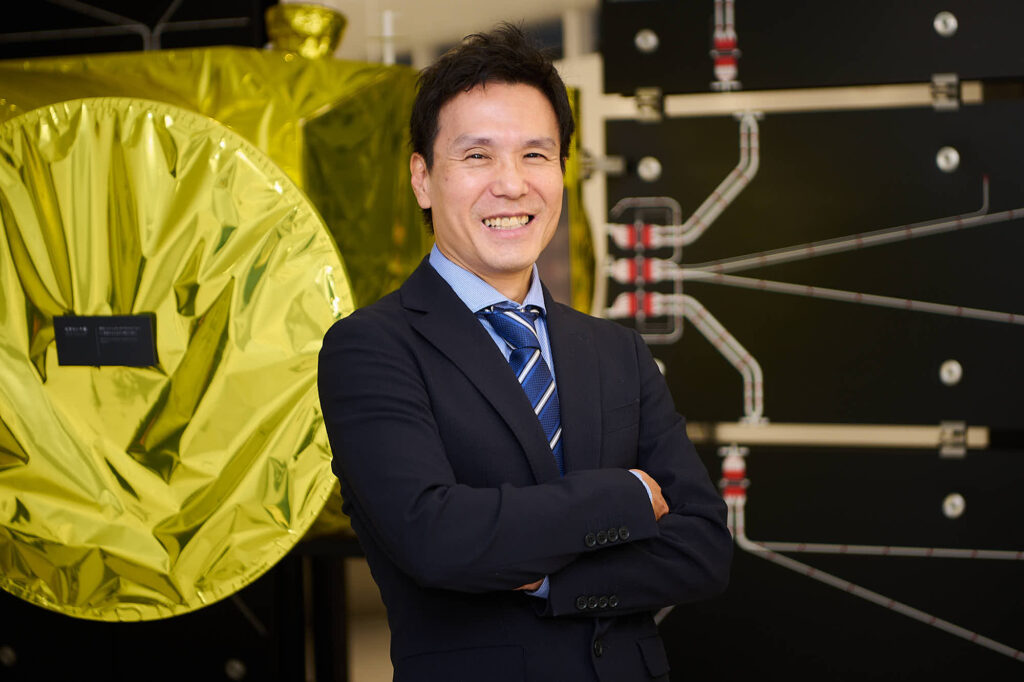
—【松嶋】吉村さんの今後が楽しみです。最後に読者へのメッセージをお願いします。
—【吉村】最後は一人の弁理士としてお話させてください。
日本ではたくさんのスタートアップが誕生していますが、知財を有効活用できている企業はまだ少ないように感じています。
日本弁理士会ではスタートアップを支援する取り組みがあり、そこで私も知財コンサルテーションのお手伝いをさせていただいております。知財を活用した事業成長に悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談いただけますと幸いです。
【クレジット】
取材・構成/松嶋活智 撮影/原哲也 企画/大芝義信
